
こんな課題はありませんか?
元請けから「建設業許可を取ってくれ」と言われたが、自力で申請は難しい。
規模の大きな工事を受注するために建設業許可が欲しい。
建設業許可を取得して公共工事を受注したい、会社の信用力を増したい。
経営事項審査を受けて公共工事を受注したい。
決算報告(決算変更届)を作成してもらいたい。
建設業許可に実績ある行政書士が確実にサポートします!
建設業許可に実績豊富な行政書士が、許可申請、経営事項審査申請、決算報告作成など、建設業許可に関するサービス全般を提供します。弊所では年間30件超の申請実績があります。面倒な書類作成は全てお任せください!
弊所の強み
- 官公庁出身で許認可申請に強い
弊所行政書士は、官公庁で許認可管理業務を数多く担当してきました。書類の要件審査、役所との交渉を得意としています。弊所では年間30件超の申請実績があり、確実な書類を作成し、お客様の許認可申請をサポートします。
- 建設会社での役員経験があり、事業経営に明るい
弊所行政書士は、建設会社(電気工事業)で取締役として、資金調達、法務統括業務を経験していますので、建設会社の経営にも通じています。書類作成だけでなく、建設会社の経営事情を理解した上で業務を進めます。
- 地元密着で迅速に支援します
国立市在住・在勤で、府中市、立川市、八王子市をはじめとした多摩地域が地元ですので、車でどこでも出張可能です。土日夜間も、電話対応可能です。何かあればすぐ駆け付けるフットワークが強みです。
提供サービス
- 迅速・丁寧な対応
弊所は、小規模事務所の強みを活かして、大手事務所では難しいきめ細かな対応を心がけます。もちろん、対応は迅速。ご多忙な社長様のために夜間・土日も電話対応が可能です。
- 明朗会計。後出しはしません
お見積りは契約前に明確に提示します。契約後に請求金額が変更になることはありません。弊所の料金表は、大手事務所には真似できない良心的な設定です。
- 許可取得後の維持管理も万全
建設業許可は、許可取得後も、毎年の報告や許可事項の変更のたびの届出、5年に1度の更新など、維持管理が大変です。弊所では、スケジュール管理を含めて、許可の維持管理をお任せいただけます。
解決事例
料金表
■行政書士報酬(税別)
※別途、行政庁への手数料がかかります。
| 知事許可新規 | 120,000円 |
| 大臣許可新規 | 150,000円 |
| 知事許可更新 | 70,000円 |
| 大臣許可更新 | 90,000円 |
| 決算変更届(決算報告) | 個人30,000円 法人40,000円 |
| 経営事項審査 | 90,000円 |
| 経営状況分析 | 30,000円 |
建設業許可とは
建設業とは
建設業とは、『建設工事の完成を請け負う営業』のことです。
請け負うというのは、工事の完成を約束して仕事をするということです。
建設工事とは、土木・建築に関する全ての工事を指します。
例)土木工事、とび工事、大工工事、鉄筋工事、電気工事など
建設業は法律で29種類に分類されます。
許可が必要な場合
建設業者は、下記の規模以上の事業を行う場合には、建設業許可が必要になります。
①建築一式以外の工事(専門工事)で、請負代金500万円(税込)以上の工事
②建築一式工事で、請負代金1500万円(税込)以上の工事
※木造住宅で延べ面積150平米未満のものを除く
上記の規模未満の工事は、軽微な建設工事として、許可は不要です。
ちなみに、1つの工事を1000万円と500万円の契約に分けた場合、1500万円の工事を請け負っているとみなされます。
許可の種類
建設業許可は、1つの都道府県にのみ営業所がある場合は、都道府県知事の許可、複数の都道府県に営業所が存在する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
営業所とは、請負契約に関する実態的な行為(見積り、入札、契約など)を行う事務所のことです。単に登記があるだけとか、単なる作業所のことではありません。
建設業の許可区分
建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。
元請けとして、建築一式工事の場合は7000万円、それ以外の工事は4500万円以上の工事を行う場合は、特定建設業許可が必要です。
それ以外の場合は、一般建設業許可になります。
許可の有効期間
許可の有効期間は、5年間です。
更新の手続きを怠ると失効します。
失効した場合は、再び新規申請する必要があります。
建設業許可の要件
■建設業許可の要件
一定規模以上の建設業を営む場合には、都道府県知事または国交大臣の許可が必要です。建設業許可を取るためには、主に7つの要件があります。以下に建設業許可の要件の概要を記載します。
- 経営業務の管理責任者がいること(次のいずれも必要)
①常勤であること
②一定以上の経営管理経験があること - 専任の技術者がいること(次のいずれかが必要)
①国家資格者であること
②指定学科を卒業後、一定の実務経験を有すること
③当該業種について10年以上の実務経験のあること - 請負契約について誠実性があること
建設業の請負契約について、不正や不誠実な行為をする明らかなおそれがないことです。
不正や不誠実とは、違法行為や請負契約違反(工事をきちんと履行しない、支払いの遅滞など)などのことです。 - 財産的基礎、金銭的信用があること
①一般建設業の場合
次のいずれかに該当すること
⑴自己資本500万円以上であること
⑵500万円以上の資金調達能力があること
⑶直近5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があること②特定建設業の場合
次の全てに該当すること
⑴欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
⑵流動比率が75%以上であること
⑶資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること - 欠格要件に該当しないこと
破産して復権していない、過去5年以内に建設業許可の取消しをされた、禁固以上の刑が終わってから5年以内である、反社会勢力との関連があるなど、欠格要件が定められています。
- 適切な社会保険に加入していること
①厚生年金
法人は必須です。個人事業主は従業員5人以上ならば必須です。
②健康保険
法人は必須です。個人事業主は従業員5人以上ならば必須です。
③雇用保険、労災保険
従業員がいる場合は必須です。 - 営業所があること
営業所には、次の要件があります。
①来客を受け入れ、見積りや契約等の業務を行っていること
②電話や机などの事務器具があり、独立した事務スペースがあること
③常勤の役員等がいること
④専任技術者が常勤していること
⑤営業用事務所として使用の権利があること(住居として契約しているところで営業している等は認められません)
⑥看板などで外部から建設業者であると認知できること
これらの要件をクリアしていることを行政機関に示す必要がありますが、事業者の方は本業で忙しく、手間のかかる書類作成は難しい場合があります。
行政書士に許可申請の代行を依頼すると、ご自身は本業に専念しつつ、許可申請を行うことができます。
建設業許可の審査期間
知事許可 30~60日
大臣許可 90~120日
業務の流れ
まず、ヒアリングを行い、許可の見込みを簡単に判断いたします。許可が取れそうなら、資料を確認して、本当に許可が取れるか、本格的に判断いたします。
ここまで費用はかかりません。
お客様が申請を要望される場合は、その後に契約を結び、業務を進めます。
決算報告(決算変更届)
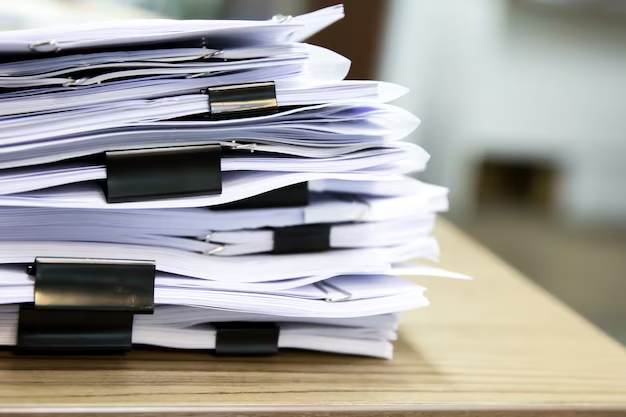
決算報告とは
決算変更届は、建設業許可を取得している事業者が、許可行政庁に毎年提出する義務のある届出です。
決算変更届には、その事業年度に行われた工事経歴や資産状況等を記載します。
提出を怠ると許可更新に支障が出ることがありますので、ご注意ください。
必要書類
決算変更届に必要な書類は以下のとおりです。
①決算変更届
②工事経歴書
③直前3年の各事業年度における工事施工金額
④財務諸表
⑤事業報告書
⑥納税証明書
提出期限
決算変更届の提出期限は、事業年度終了の日から4か月以内です。
注意点
決算変更届は、税務署に提出する決算書を、建設業法の規定にしたがって書き換えて作成します。
決算書をそのまま使うことはできません。
当事務所のサービス
当事務所では、決算変更届の作成を承ります。経営事項審査なども見据えて、企業の信用性を守る書類を責任もって作成いたします。
お問合せ
建設業許可申請代行、決算報告、経営事項審査申請代行を行政書士が行います。
《対象エリア》
立川市、府中市、八王子市、町田市、国分寺市、国立市、多摩市、日野市、小平市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、小金井市、武蔵村山市、東村山市、西東京市、昭島市、福生市等の多摩地域中心に東京都内全域で建設業許可申請代行を行政書士が行います。
「営業所要件」でNGに…自宅兼事務所で建設業許可を取得する際の盲点とクリア条件
社会保険未加入では許可が取れない?建設業許可と「社会保険加入義務」のリアルな実情と対策
「専任技術者」は実務経験10年だけじゃない!あなたの会社に眠る「隠れた資格」で要件をクリアする方法
公共工事に参入したい!「経営事項審査(経審)」で評点を上げ、受注額をアップさせる戦略とは
【実録】建設業許可が取れない…事業者が陥りがちな「落とし穴」トップ5とその回避策
建設業許可は「取って終わり」じゃない!5年ごとの更新と「毎年の決算変更届」を忘れる恐怖
元請けから「許可取って」と言われたら?最短で建設業許可を取得する実践的ロードマップ
【要件クリア術】「経営業務の管理責任者(経管)」が見つからない…!その場合の3つの対処法と裏ワザ
「500万円未満だから大丈夫」は危険?建設業許可が「今すぐ」必要になる3つのケース
500万円の「残高証明」が取れない…。「財産的基礎」要件をクリアする別の方法を行政書士が伝授
建設業許可や決算変更届に必要な「工事経歴書」の書き方をわかりやすく解説!
建設業許可の社会保険加入要件とは?― 未加入は許可が下りない時代へ
建設業許可における営業所要件とは? ― 本店・支店の実態が問われる重要ポイント
建設業許可における専任技術者とは?その要件と実務ポイント
建設業許可取得に必須!経営業務管理責任者(経管)の要件とは
建設業許可の有効期限と更新手続きの注意点
建設業許可が必要な工事とは?500万円の壁に注意!
財産的基礎とは?自己資本要件と直前決算の確認方法を解説【建設業許可】
公共工事を目指すなら必須!経営事項審査(経審)の基礎知識
専任技術者とは?建設業許可に必要な資格・実務経験の要件をわかりやすく解説
建設業許可のカギを握る「経営業務の管理責任者(経管)」とは?要件と不足時の対応策を徹底解説
許可が取れない!建設業許可のよくある落とし穴と回避策
建設業許可の7つの要件とは?取得に必要な条件を総まとめ
建設キャリアアップシステム(CCUS)とは?行政書士が解説します。
建設業許可取得後に必要な手続きとは?
建設業許可が必要なタイミングとよくある誤解
行政書士がわかりやすく解説「建設業許可を取得するメリットとは?」
行政書士がわかりやすく解説「建設業許可の種類とは?」
建設業許可を取得しないとどうなる?
行政書士がわかりやすく解説「建設業許可が必要な工事とは?」

